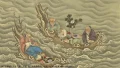この記事は他ブログで2010年に書いた記事の引越版です。今回は大分加筆修正しております。
今回は、直接歴史に関係する本ではありませんが、「文化論」のような意味で取り上げてみたいと思います。それはシェル・シルバスタインのロングセラー『おおきな木』です。(邦訳は本田錦一郎氏)
2010年にこのブログを書いた際は本田錦一郎氏の翻訳が前提でした。70年代の本で翻訳者も故人となり絶版になっていたようですが、新しい出版社から村上春樹氏による新訳が出ています。下記写真も今回の記事転載にあたって村上春樹氏の新訳に差し替えております。
先ず、本論に入る前にですが、私としてはこの邦題が気に入らないのです。原題はThe Giving Treeつまり「与える木」です。本当はこの題にこそこの本のポイントがあると思うのですが、やはり対象年齢を考えた促販やわかりさすさという点で「おおきな木」にせざるを得なかったのでしょうか。尤も、「寛大」という意味の「大」を平仮名の優しさと共に表現しているのかもしれませんけれども。
あらすじ
さて、内容は「木」と「少年」の物語です。「木」は少年に様々なものを与え、「少年」は子供の頃から大人になるまで、「木」の恩恵を受け続けるというストーリーです。もう少しわかりやすくまとめると・・
という感じの筋立てです。あまりネタバレすると宜しくないのでこの辺で。
感想や一般的評価
この本の読み方、解釈は人によっていろいろです。「少年」は「木」に依存しているのは明らかですが、「木」も「少年」に依存している共依存だと見る人もいます。(少年は度々木を忘れて去ってゆくわけですが)。何か哲学的な教訓を見出す人もいると思います。また、批判も昔から多く、ただ不愉快なだけの話と言う人もいます。
私はこの話が若い頃から好きで、ただ単純に、「見返り無く与える木の幸福」の話だと思っています。もちろん、「少年」はいつまでも「利己的」で要求ばかりします。でも、木は与える気持ちを決してなくしません。これは単純に言えば、キリスト教的な利他愛ということでしょう。(もちろん作者自身は取り立てて一定の社会的メッセージを込めた訳ではないと言っています)。
結局、「与える人は強い」という話だというのが私流の勝手な解釈です。ただし、常に与えればうまく行くとか、幸福感に満たされるということでもありません。私が思うに「木」は神ではありません。やはり気持ちの揺れはあるのです。でもやっぱり愛する対象(家族でも、それ以外でも)には何かをしてあげたいし、難しい時期があっても、結局また戻ってくる場所であることは幸福なことだと思うのです。(来ないこともまああるけれども)。まあちょっと「休憩していきなさい」と言える気持ち(の余裕)は結局幸せなのだろうと考えるのです。(これは私が生涯苦手とする部分で、憧れでもあります)。
そして面白いのは、この本を読む人たちの文化圏によってもかなり感じ方が違うということです。この点は次に紹介する関連書からちょっとまとめてみたいと思います。
守屋慶子さんの『子どもとファンタジー』
ご紹介するのは、守屋慶子さんの『子どもとファンタジー:絵本による子どもの自己の発見』です。これは、上記の『おおきな木』を題材にした子供たちの研究書です。詳細は是非読んでいただきたいのですが、日本・スウェーデン・イギリス・韓国の合計4カ国の子供たちが『おおきな木』を読んでどんな感想を持ったかを分析したものです。(ちなみに、守屋さんの本では『与える木』と呼んでいるところがとてもうれしいところ)。
例えば、キリスト教文化圏においては、「木」に聖書の神を見るケースが多いようです。キリスト教文化の中では「少年」は自らーつまり人間を指し、神から与えられるばかりの存在で反省しないといけない・・という感じでしょうか。
この『子どもとファンタジー』では、各国の子供達の傾向や、年齢層による変化など多様な角度から調査分析がなされています。特に、日本の現代社会についての分析はなるほどと思うところがありました。
たとえば、日本人は人から何かをしてもらう行為を大変恐縮に感じる国民性があるわけですが、その点を次のように評しています。
「少年は何でも自分でやるべきだ・・・」という感想が日本の子供に多い。親切は無償だからこそそれを受けてはならない、受けないようにしなければならないのである。相応のお返しを期待する社会、文化では「親切」が対人関係にあって円滑に機能しうるが、日本の社会では無償であるべきと考えられるためにかえってうまく機能しないという皮肉な結果になっている。
『子供とファンタジー』P174 (太字下線は筆者)
つまり、日本の子どもたちは、「少年はお返しをしていないからひどい」と考える子が多い調査結果だったわけですが、裏を返せばそれは日本の社会構造が「頂くとお返しせねばならない」(無償でもらうべきではない)ものになっているということです。なかなか面白い指摘です。(これについては諸説あるかとは思います)
この本についての朝日新聞の「天声人語」の評も一部以下に紹介します。
(日本の子どもには)木に助けられる少年に批判的な見方が多いことから、日本では競争的な対人関係はあっても「助け・助けられる」関係は市民権を得ていないのではないか、とも(本書は)指摘している。考えさせられる。
「朝日新聞」1995年1月8日。(括弧内は筆者補足)
また、「木は果たして幸せだったかどうか」という点についての感想も国によって分かれる傾向があったようです。日本の子どもは「本当は木は幸せじゃなかった」と考える場合が多いのに対し、西欧や韓国の子ども達はそのまま「幸せだった」ととらえる傾向があるようです。これはいろいろな意見があって良いわけなので正解はありませんが、大変面白い調査結果です。
確かに守屋さんの指摘は、今の世の中を考える一助になると思います。そしてまた、『おおきな木』をより多面的に見るための良い参考書でもありました。
朝日新聞の「天声人語」の切り抜きが本に挟まっていました。本も切り抜きもちょっと黄ばんでますが、写真をば・・。
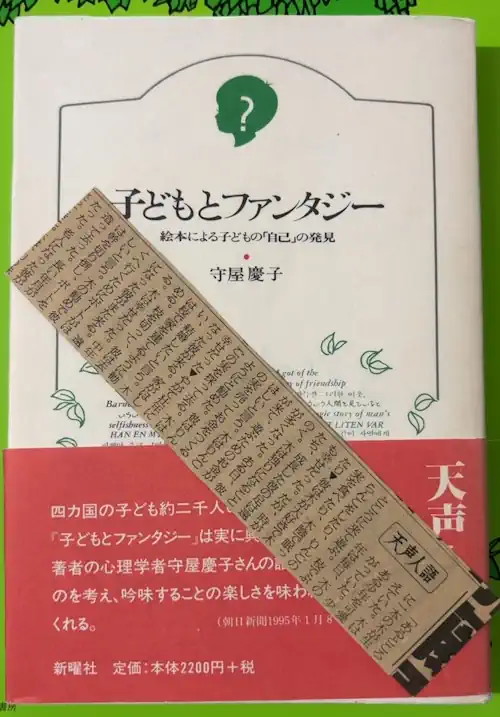
まとめ
いずれにしても今回、改めてシルバスタインの『おおきな木』を読み直し、同時に守屋さんの考察本を拝読して、物事をちょっと深く考えてみる大切さ、楽しさを感じました。
いろいろ理屈を書き連ねましたが、のんびりと子どもに戻って、絵本をただ眺めるのもいいですよね!
以上お読みいただき感謝いたします。
(2010年5月11日)
このブログを書いた直後に村上春樹訳が出ました。(2010年9月)。それで、旧版・新版の翻訳の比較で感じたことを追記としてまとめておきたいと思います。(英語は全く素人なので、間違っている点があるかもしれませんが)。
全体的な翻訳の勝手なイメージはこんな感じでしょうか。
ちなみに、私が以前から気になっている部分が一つあります。これは特に村上訳が出てからさらに気になっている部分です。それは、後半で幹を切り倒して切り株だけになってしまったあとのナレーションです。
And the tree was happy… but not really.
この英文の翻訳はこんな感じです。
私は村上訳がでて、その翻訳の正確さは素晴らしいと感じていましたが、この部分にきてちょっと戸惑いました。あまりに二つの翻訳が違うからです。もちろん、本田訳はあきあらかに意訳ではあります。でも、村上訳があまりに断定的だったことに違和感を覚えました。
どちらが正しいということはないのでしょうけれども、やはり私は本田訳の「ほんとかな」という問いかけが好きです。私は上記2010年に書いた部分で、「見返り無く与える木の幸福の話だと思う」と書いたこともあって、この部分をずっと考えてきました。村上訳の「なれませんよね」は、直訳としては意味が近いかもしれませんが、ちょっと悲しいのです。もちろん、この一文はあくまで「切り株」になった時点だけのものとも解釈できますけれども、私としては全体の印象に影響を与えているように思います。
この点で私はヒントがあると勝手に思っています。実はその昔シルバスタインご本人の朗読アニメというのが公開されています。youtubeにもあったので一応貼っておきます。
このアニメは、本そのままの朗読版ではありません。実はかなり本とは違うのです。彼自身が物語を語り直している、演じているかのようです。そこで注目したいのは、上記の”And the tree was happy… but not really.”の部分なのです。なんとこのアニメでは、”but not really”がないのです。多分、これが一つの答えなのかなと勝手に思っています。やっぱり(ちょっとがっかりしたこともあったけど)木は幸せだったのだろうと。(もちろん解釈は引き続き自由であることはかわりないのですが)。いずれにしても、とっても味のある朗読です。
あと、守屋さんの本については、上記翻訳の問題を考えるようになってから、その点がほとんど言及されていない点を残念に思うようになりました。各国の子供たちは、翻訳版である以上「厳密に言うと同じ話を読んでいない」ことはかなり重要ではと思うようになったのです。(もちろんこれは釈迦に説法ですが)。
例えば、木が男か女かということなども大きく印象を変えると思います。英文では木は”she”で「女性」のようであり、村上訳は明らかに台詞は女性言葉です。一方の本田訳は、そのまま読んでいると男性かなとも読めるので、訳し方一つで変わるなと感じます。そして、それが外国の言葉であればまた変わってくるわけです。(母性を感じるとか、神だと感じるとか)。
この翻訳の問題については素人の私にはこれ以上は荷が重いので、このあたりにいたします。
以上、15年前のブログ内容があまりに薄かったので、追記させていただきました。