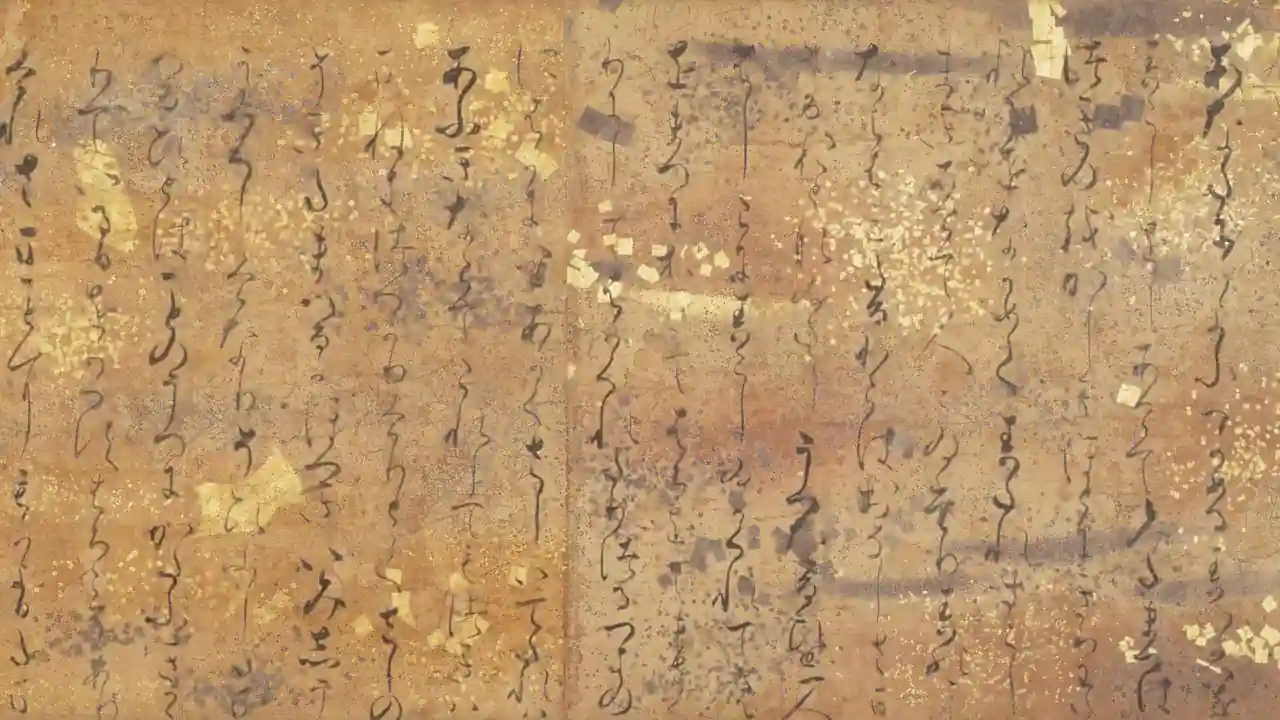毎度「天邪鬼」な大河ドラマレビューを書いております。批判的な分析を主旨としておりますため、世間一般の論調とはかなり乖離しているかと思います。そのため、ご不快に思われる方もおられるかもしれません。前もってお詫びいたします。(以下ネタバレも含みます)。素人の自由研究レベルでありますので、誤りがありましたらご容赦ください。
第29話「母として」感想
今回は、夫宣孝の突然の死や、父為時が再就職を断るなど「まひろ」の身辺にもいろいろありました。
毎度思うのですが、清少納言の描き方はかなり無理があると感じます。もちろん、ファーストサマーウイカさんの演技に不満はなく(なにか中毒性があり・・)、毎度登場を楽しみにしております。ただ、彼女はあくまで実在の人物なので、あまりにアレンジが過ぎるのもどうかと思うのです。清少納言は、紫式部の夫宣孝についてかなり辛口な記述をしており、本来的に二人は水と油なはずです。それを前半ではかなり親密な関係に描いたことにそもそも無理があったと思います。おそらく顔を合わせたこともないと思われる二人の関係を、行き来のある(今回もわざわざ訪ねてきた)関係性として描くのはフィクションだとしても無理があると感じます。
特に紫式部の彼女への感情は、お互いを知らないからこその尊敬、嫉妬、不快感なのだと思います。今回、二人の関係が急速に悪化するような演出をするのも違和感がありました。ドラマの「まひろ」は、『枕草子』の感想を求められた際に、「定子の負の部分も描写したら良い」と評しましたが、実際の紫式部が注目したのは(不快に感じたのは)、清少納言が表面的な知識をひけらかしているという点でした。(これはあくまで彼女の主観ですが)。この点はかなり重要だと思うので、そこが曖昧になってしまっているのは残念です。まあ、これまでのストーリーからすれば、そんな批判を突然ここで展開できるわけもありませんが・・。今後二人の関係性がどのように描かれてゆくのか、注目したいと思います。
詮子の命により、敦康親王を「人質」として迎える場面がありました。史実では定子亡き後、一条側近である藤原行成の説得もあって敦康親王を彰子のもとで養育させるようになります。それでも定子亡き後の一条の気持ちは彰子には向きません。長保三年閏12月22日(1002年2月)に母詮子が死去すると、なんと、敦康の「御母代」として彰子の元に仕えていた定子妹の御匣殿が一条天皇のお手つきになってしまいます。その結果御匣殿は懐妊します。道長たちはそうとう焦ったものと思われます。しかし結局懐妊中の長保四年(1002年)夏に亡くなります。(この辺は次週描かれるのかもしれませんが)。
この頃には、道長と一条の間の関係はかなり悪化しつつあったと言えます。定子の死についてほとんど黙殺した道長に対し、一条が母詮子の死について悲しみを表す記録もありません。ドラマ監修の倉本一宏氏は「定子が崩じた際の道長の態度に対する意趣返しの観もある」1と述べておられます。実の母のことと考えると、なんとも複雑な気持ちにはなります。
詮子は病気平癒を願って伊周の官位を戻すように一条天皇へ願います。前年道長が同様に願った際は、形式的には却下されましたが、やはり一条天皇としては乗り気だったのでしょう。
ただ一方で、改めて伊周の「厄介さ」も感じました。彼の不運はたしかに気の毒ではありますが、あまりに往生際が悪いと、身を滅ぼすという典型かもしれません。容姿にも才能にも恵まれた人だったようですから、残念なことです。ただ、「往生際が悪い」という表現を使いましたが、それはあくまで私たちが後世の人間であり事の顛末(歴史)を知っているからです。当時はまだ彰子も懐妊しておらず、復位を赦されたとなれば再び過去の栄光を取り戻そうとするのも当然ではあります。(それにしてもやり方が・・・とは思いますが)。
弟の隆家は兄とは対照的な生き方をします。彼は道長に近づき、実資にもかわいがられました。(度々相談に乗っている)。ただそれは、彼なりに「中関白家」の再興をさぐる生き方でした。今後ドラマで彼がどのように描かれるのかにも注目です。
伊周、隆家兄弟については、ドラマ監修の倉本氏の以下の著書が秀逸です。ただし、『源氏物語』『枕草子』などの文学については一部(素人が僭越ながら)首肯できない部分がありました。文学については他の参考書も参照されることをお勧めいたします。(尤も、著者は文学については専門外であることを認識しておられ、色々な学説を参照しての解説ですが)。
道長が「ぶちキレた」話
品のない見出しで申しわけありません。
詮子の四十歳を祝う儀式では、道長の嫡男田鶴(後の頼通)の舞よりも異母弟巖(後の頼宗)の舞の方が一条に高く評価され微妙な空気になる場面がありました。
史実では微妙どころではなく、この時道長は愛する嫡男がないがしろにされたと不満を表し(キレて)、退出してしまうという騒ぎになっています。この儀式は二日前にリハーサルが行われていて、そのときは嫡男田鶴の舞が一条に褒められていたので、道長にとっては思わぬ出来事だったのかもしれません。ただ実はリハーサルの時も舞の出来としては弟の方が評判がよかったのです。藤原行成はその日記『権記』で「納蘇利<巌君。>。舞の腰、天骨を得。神妙と謂ふべし。」(長保三年十月七日条)とリハーサルでの弟巖の舞を褒めています。
本番でもやはり弟の出来が良く、一条天皇は弟の舞の師範を叙爵することで弟の方が優れていることを示しました。そのときの様子を藤原実資は『小右記』にこう記録しています。
納蘇利(弟の巌が踊った舞)、極めて優玅。主上(一条天皇)、感ぜしめ給ふ気有り。上下、感歎し、涙を拭ふ者衆し。右大臣(藤原顕光)、事の由を奏す。天許有り。爵を右兵衛尉多吉茂に賜ふ。(巌の舞の師範だった多吉[好]茂に栄爵があった)。・・(中略)・・・。□□心に怨色□、座を起ち、解脱して、臥内に入る。(道長は怨む様子があり、座を立って寝所に入ってしまった)。時の人奇しむ。「陵王の兄(兄の田鶴)、既に愛子たり、中宮(彰子)の弟、当腹(倫子)の長子。納蘇利(弟の巌)は外腹の子(側室明子の子)。其の愛、猶ほ浅し。今、納蘇利の師を賞せらる。仍りて忿怒する所」と云々。
摂関期古記録データベース『小右記』長保三年(1001年) 十月九日条書き下しより(『野府記』版本。赤字筆者)
「キレた」道長は暫く戻ってこなかったようですが、一条がなだめてようやく戻ったと言います。それでも憤懣やるかたなく、一条天皇のお泊まりや翌日の競べ馬も中止にしたとのこと。(自宅での私的な集いとは言え、来客も多いわけで相当傍若無人です・・)。一条天皇としては顕光の上奏もあり、リハーサルで既に嫡男を賞しているので次男も・・と考えただけなのかもしれません。(しかも本人ではなく師範を賞したのは道長に気を遣ったとも思えます)。
同じ自分の子でも、愛する嫡子の面子が潰されたことに耐えられなかったのでしょうけれども、引きこもってしまうあたりは、大人げない所業ではあります。ドラマではこの辺をかなり省略し、道長を美化しているのが残念です。もっと道長を複雑な人間(醜い部分も含めて)描いてほしいものです。(今回「まひろ」が清少納言に言った通りに・・)。
ちなみに「納曽利(納蘇利)」は、右方舞と呼ばれ朝鮮半島起源の雅楽。高麗楽とも。名称の由来は地名説や朝鮮語「ナ(儺)ソリ(歌)」説2など諸説あり。朝鮮半島由来であり、追儺という性質を考えると、そのまま翻字しものかもしれません。
また「陵王(蘭陵王)」は、納曽利と対をなす左方舞で中国唐起源の雅楽。北斉の皇族高長恭(蘭陵王)が名称の由来。北斉の名将で、その悲劇性故にも伝説となった人物です。美貌故に戦場では面をかぶっていたという伝説が発展してこの舞になったとのこと。
まとめ
今回の題「母として」は、「まひろ」だけではなく、詮子や倫子、明子らのことも指すのでしょう。そういえば彰子も、名目上とはいえ若くして養母としての務めを担うことになりました。さらにちょっとだけでしたが、伊周の息子松の母(源重光の娘。松田るかさん演じる)も登場しました。この松が後に悪三位と言われた放蕩者藤原道雅であることを考えると、なんだか悲しい気持ちにもなります。当然ですが、物語の背後には多くの母達がいるのですね。
このころの道長の政権基盤は、まだもろさを含んでおり、全ては彰子の懐妊にかかっていました。このような複雑な状況で、定子サロンへの思慕やまぬ一条の心をなんとか彰子に向けようとして、いよいよ「まひろ」を女房に・・・と話は進むのでしょう。彰子がどのように変わって行くのかも楽しみです。