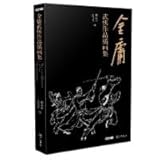この記事は、2024年に他ブログで書いたものの引越版です。一部加筆修正しております。
ずっと疑問に思っていたのが、古装片(中国の歴史映画やドラマ)はなぜ「総髪」ではなく、髪を後ろに垂らしているかつら(披发)が多いのか?という問題です。(アイキャッチ画像は明の名画家仇英が周王を描いたものですが、庶民たちも皆総髪で描かれています)。
▲こう感じの髪型(男性の方)。Amazon music一念关山OSTより引用。
今や多くの古装・武侠映画やドラマで使われており、私はどうも以前から苦手なのです。(これは私の勝手な印象で、歴史や小説ベースで見てしまうからでしょう)。中国でもこの点を疑問に思う人は未だに多くいます。ただ、若い世代を中心に多くの古装ドラマファンは「これが当然」と思うようになってもいます。アニメやゲームの影響もあるでしょう。確かに、イケメン俳優はより美しく見えるでしょうし、悪役はより怪しく見えるでしょう。中華圏においては、かなり普及した髪型(かつら)と言えます。
ここで考えるのは、いいか悪いかではなくて、どういう経緯でそうなったかです。同時に、歴史や文化の問題でもあるので、ある程度史実的な問題もまとめて見ます。
金庸武侠小説の挿絵を見てみる
有名な金庸の武侠小説の初期の挿絵では、まだそのような髪型は出てきません。金庸の作品の多くは時代背景に史実があり、挿絵の時代考証もある程度しっかりしていて、「射鵰三部作 」や「天龍八部」などはいずれも総髪で描かれています。
以下は、金庸の武侠小説の挿絵。(画:姜雲行)。男性は総髪、女性は髷を結っています。


50年代から70年代まで、金庸小説の挿絵は姜雲行と王司馬が担当しました。姜雲行の画は非常に綿密に考証してかかれていて、金庸からも信頼されていました。挿絵につきましては、以前に別稿で書いております。
現在の映像作品
現在のドラマにおいての大まかな区分としては、時代背景が濃いものの場合総髪にしている場合が多く、フィクション性が高かったり、武侠・無頼などのキャラクターイメージを優先するばあいは、垂れ髪にする場合が多いようです。
例えば、「琅琊榜」は、架空の設定ではありますが、政治的な闘争が多いこともあり、いずれもきちんと総髪です。(例外もいる)。

一方で、「蒼穹の剣」は、架空かつファンタジーなので、垂れ髪になっています。雰囲気の違いは明白です。(もっとも、ファンタジーならなんでもかまわないわけですけれど)。ちなみに主役の呉磊は、上の「琅琊榜」にも子役で(写真右)出演していました。いい俳優さんになりました。
▲Amazon 蒼穹の剣DVD-BOX1【日本語字幕版】 より
髪を結うこと
古来中国では、髪をまとめることは重要な礼儀作法でした。荀子は髪を崩している人達を、「女々しい髪型」として批判しています。また、髷を切るという行為は「死」を意味するほど重要な意味がありました。(たとえば、三国志では、曹操が自らが定めた軍令を破った際に、将帥の自分が死罪にはなれないのでと自分の髷を切る場面がありました)。
いずれにしても、中国では髷をしないとか、髷があるのに髪を垂らすという習慣はありませんでした。特に一般庶民の場合、礼儀の問題以前に、長い髪は労働する際に不自由かつ危険なので、髷を作ったり結ったりしていました。また、侠客や鏢師、兵士など戦闘に関わる人達は髪が邪魔になると命に関わるわけで、なおさらきちんとまとめていたようです。
古代中国では20才になると冠を付けるようになることから、20才の男子を「弱冠」というようになりました。これも成人男性はきちんと髪を束ねているべきだという価値観の表れです。
補足:辮髪
例外的に清代(元なども)は辮髪でした。これは元々騎馬で戦闘する際の利便性から来ている習慣と言われます。それでも、後ろに髪を残したのは、やはり髪を神聖視する慣習があるからのようです。
実際の辮髪は時代によって後頭部に残す髪の面積が違ったと言われます。入関前後はコインぐらいの面積しか残さず三つ編みも細かったと言われますが、後にだんだん残す面積が増えたようです。(古装劇でみるような形)
清末になると西洋の影響や軍事的な側面(安全面等)から辮髪廃止論も上がります。また革命期からはナショナリズムと結びついて、知識人の間に「辮髪を切らないと明までのご先祖に申し訳ない」として嫌悪が広がります。ただ、一方で見落としがちなのは、当初一般庶民の多くが、「辮髪を切るなんてご先祖様に申し訳が立たない」とも考えたということです。1 庶民の「ご先祖」はあくまで身近な人達のことでした。かの魯迅も、漢満の違いなど意識したことがなかったと著作で述べています。清初にあれほど激しい抵抗を受けた「辮髪」も、数百年を経てごく当然の習慣になっていたのです。この辺の「普通の人達」の心性史のようなものも、もっと注目されるといいなと思います。
なぜ垂れ髪が始まったのか?
では次に、なぜ歴史的にはあり得ない髪型が古装ドラマ界で始まったのか、経緯をまとめてみたいと思います。(あくまで私の勝手な調査とまとめです)。
見栄え・利便性の問題
ドラマで後ろに髪を伸ばす形態のかつらが使われようになった理由の一つは、単純に見栄えの問題が挙げられます。主役俳優からすれば、垂れ髪のかつらは、前髪を含めて全てを束ねてしまう総髪と比べてほとんど普段のイメージと変わらないため、重宝されているようです。昔から「カツラののりが良い(悪い)」などと言われるように、「似合うかどうか」も大きな問題ではあります。
さらには、かつらの装着が容易であるということは大きいようです。頭の後ろ側の髪をうまく処理するのはなかなか手間で、かつらを接着するのりの必要性や、メイクアップの手間や時間などを考えると、後ろ髪を隠せる(処理しなくてよい)「髷+垂れ髪」のカツラは利便性も大きいようです。
香港・台湾映画の影響
歴史的には、金庸や梁羽生、古龍のドラマなどがブームとなる香港武侠映画の時代が起源だとする見解が多いように思います。
1950年代までは古装ドラマでも総髪であるものが多いですが、特に70年前後から後ろ髪が長くなって行くようです。70年代の金庸系列のドラマの多くは既に「襟足の毛」が多少伸びた状態のかつらです。ここにはやはりかつらの簡便化が関係している気がしますが、「カンフー映画」では頭頂部を剃らない辮髪も良く登場するので、「簡便さ」と「見栄え」の問題があったのでしょう。
▼以下は2003年版の「射鵰英雄伝 」の郭靖です。ここではまた総髪が復活しています。(張紀中監督作品ということもあるかも)
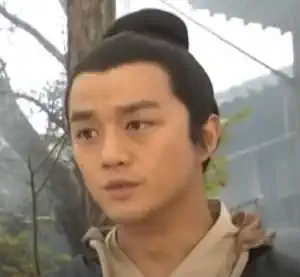
歴史とファンタジー
結局、史実を背景に持つ話の場合、やはりこのあたりの考証をしっかりすることが質の高いドラマとして重要な要素になって行くものと思います。金庸や梁羽生(近年では馬伯庸など)のように歴史的背景が濃い武侠・歴史ドラマは、是非細かいところまでこだわった映像化を望みたいものです。もちろん武侠小説につきものの「怪異なキャラ」とか「奇人」は、イメージもありますから、自由な風体で良いとは思います。このような願いを持つ視聴者も中国ではまだ多いので、今後の映像化作品にも注目したいと思います。
一方で、近年では異世界ファンタジー(ハイファンタジー)に振り切った古装(風)ドラマも大変多く作られています。WEB小説を始め、架空の世界を舞台にした優れた原作小説が近年多く登場していることも背景にはあるのでしょう。結果として、映像化された作品も、既成概念にとらわれない自由なキャラクター描写になっています。その意味では、カツラや衣装も自由なわけですし、制作側としても利便性が高いということになります。
また、最近のドラマのレビューは、内容以上に、男性主人公が「ハンサム」であるかどうかや、女性主人公が「美しいか」を重視するレビューが多いのに驚きます。これは中国特有のものなのかもしれませんが、このようなニーズに応える為にも、「垂れ髪」のカツラは重要なアイテムとなっているのかもしれません。また、特に若い世代の男性がかっこいいと思う「侠客」像なども、アニメやゲームの影響もあって変化してきてはいるのでしょう。
まとめ
今回は「垂れ髪」のカツラについてまとめて見ました。歴史的にはあり得ないものですが、娯楽作品としての一つの「表現」というか「様式」になり始めているということなのでしょう。また何十年後かには、さらに変わって行くのかもしれません。
ちなみに、今回は女性の髪型(カツラ)については考えませんでしたが、やはり同じく批判はあります。ただ、女性の髪型の場合は、時代によって非常に多様であり、一言では説明できません。日本の平安貴族のように「結ばない」というケースはほとんど無く、長い「垂れ髪」を作る時代も少ない気がします。(漢代や宋代など?)。発掘される俑や絵画などからすると、基本的には髷を上か後ろに作っていました。庶民であれば、やはり束ねたり髷を作らないと労働できない事情もあるでしょう。近年は漢服や「古風漫画」(時代劇風の漫画)の流行などもあって、関心は高まっているようです。
今回まとめた、「垂れ髪カツラ」の歴史的な経緯や、歴史考証の問題は、結局は「何を表現したいか」や、「何にこだわるか」という問題なのでしょう。史実ものであれば時代考証は重要ですが、結局は娯楽ですから、魅力的な作品かどうかが一番重要なことです。私としては、時代の変化を感じながら、「いいな」と思った作品を引き続き(いろいろと突っ込みを入れながら)楽しんでゆくようにしたいと思います。
以上、長文お読みいただきありがとうございました。
(2024年2月7日)
参考:服飾関連の本をいくつか
- 莊文瀾「『民立報』からみる辮髪男性のイメージ」2022 ↩︎